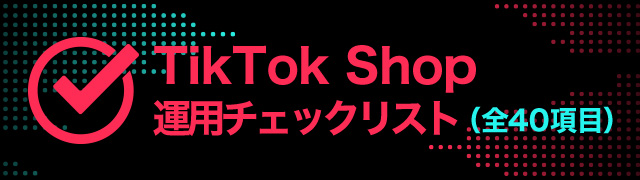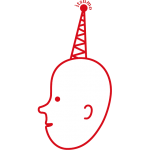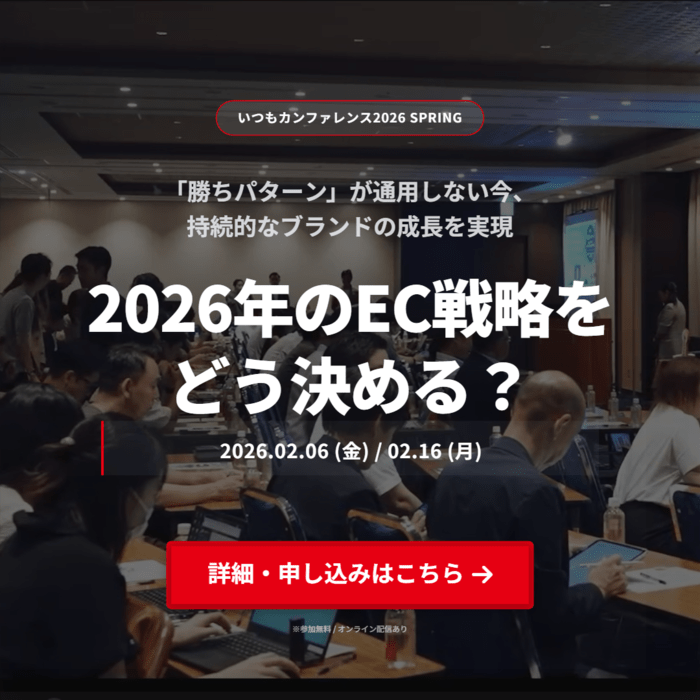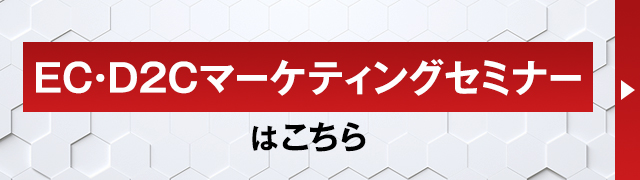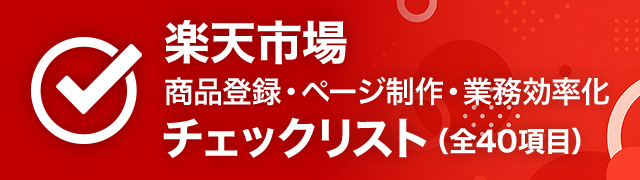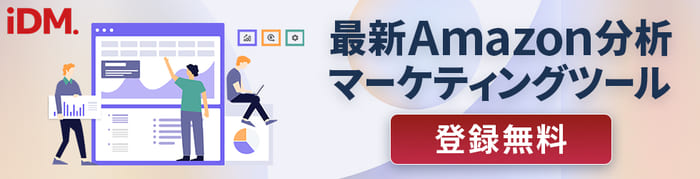ソーシャルコマースとは?成功事例から学ぶ活用ポイントと注意点

- 「SNSで発信しているのに、商品が売れない」
- 「広告費をかけずにもっと効率的に集客したい」
このように悩んでいるEC運営者や企業の担当者の方も多いのではないでしょうか。
EC市場の競争は激化しており、ただ商品を並べただけでは、購入までつながりにくくなってきています。
また、集客の方法としてSNSを活用していても、フォロワーが売上に直結しておらず、どのように商品を売っていけばいいかわからないという方も多いでしょう。
実は今「ソーシャルコマース」というSNS上での反応から購買行動につなげられる新しい販売スタイルが注目を集めています。
本記事では、ソーシャルコマースの基本的な仕組みや成功のポイント、導入時の注意点までを解説します。
SNSを活用して商品をもっと売りたい、新たな販売チャネルを探している方は、ぜひご覧ください。
※閲覧時期により本記事でご紹介の情報は変更・更新されている場合がございます。
ソーシャルコマースとは?

ソーシャルコマースとは、SNS(ソーシャルメディア)とEC(イーコマース)を活用して商品やサービスを販売する仕組みを指します。
InstagramやTikTok、X(旧Twitter)などのプラットフォーム上で、ユーザーが紹介した商品をそのまま購入できる流れがソーシャルコマースの代表例です。
近年、消費者の購買行動は急速に変化してきています。
今までは、ソーシャルメディアや検索エンジンで情報収集したうえで、ECサイトで購入する流れでしたが、ソーシャルメディアだけで購入まで完結する流れが生まれつつあります。
このような流れの中で注目されているのが「ソーシャルコマース」です。
ソーシャルコマースでは、ユーザー同士の信頼関係や体験の共有といった「オンライン上でのコミュニケーション」が購買行動に影響を与えます。
では、Eコマースとソーシャルコマースでは、具体的にどのような点が異なるのでしょうか。
Eコマースとの違い
Eコマースとソーシャルコマースには、SNSの活用方法に大きな違いがあります。
Eコマースでは、広告や検索エンジン・SNSなどさまざまなチャネルを利用して集客を行います。
SNSは集客チャネルのうちの1つである、新商品やブランドストーリーの発信など、商品やブランドを知ってもらうためにのみ使用されています。
一方、ソーシャルコマースでは、SNSを利用して集客から販売までを完結することが可能です。
双方向のコミュニケーションが可能なSNS上で情報を発信することで、さまざまな意見が飛び交います。
ユーザーはそれらを見ながらその場で購入判断を下し、欲しい場合にはECサイトにも移動せずそのまま購入できるため、販売機会を逃すことが少なくなるでしょう。
ソーシャルコマースが注目される背景
ソーシャルコマースが注目を集める背景には、いくつかの要因があります。
まず、消費者の消費購入の意思決定プロセスにおいて「口コミ」や「信頼できる人からの紹介」がますます重視されてきているという変化が関係しています。
従来のような一方的な広告よりも、知人やインフルエンサーなど「信頼できる人の紹介」のほうが購入動機として有効になってきているのです。
また、情報収集から購入までをすべてアプリ内で完結させたいというニーズが高まっていることも関係しています。
そこに加えて、Instagramのショッピング機能やTikTokのライブコマース機能など、SNSプラットフォーム自体が「商品を売れる環境」になってきていることも大きな要因です。
企業目線で見てみると、ECサイトに移動せず購入までを完結させられるため、ECサイトへの移動時間で購買意欲が低下するといった事態も避けられます。
販売チャネルの増加という観点だけでなく、売上アップも期待できることから企業からの注目も集まっているのです。
ソーシャルコマースの市場規模と成長予測

ソーシャルコマースは、新しいマーケティングの手法として世界的に定着しつつあり、今後も市場は急拡大していくと予測されています。
実際、Straits Researchの最新レポートによれば、2022年時点のソーシャルコマースの世界市場規模は5,758億米ドルとされており、2031年には6兆1,911億3,000万米ドルにまで達する見込みです。
これはCAGR(年平均成長率)30.2%という非常に高い成長率です。
急成長が予測される背景には、InstagramやTikTokなどのプラットフォームがショッピング機能を開発し、アプリ内での決済や投稿との連携によって、SNS上で購入までを実現できるようになったことも大きく影響しています。
日本でも、Z世代を中心に「SNSで見た商品をすぐに購入する」「インフルエンサーのおすすめで買う」といった行動は一般化しつつあります。
ソーシャルコマースは単なる販促手法ではなく、新たな購入体験として、今後のマーケティング戦略において欠かせない要素となっていくでしょう。
また、これからソーシャルコマースを導入しようとする企業向けに、支援サービスも充実しつつあります。
例えば、Shopifyでは、導入手順や連携方法に関する公式の資料が公開されており、初めて取り組む方でも手順通りに進めることで始めることが可能です。
参考:Shopify公式HP|SNSでショップを始める方法
ソーシャルコマースの主な形態

ひとくちに「ソーシャルコマース」と言っても、その手法にはさまざまな種類があります。
ソーシャルコマースの成功には、企業の戦略やターゲット層に応じて最適な型を選ぶことが欠かせません。
以下では、代表的な7つの型について、それぞれの特徴や活用シーンを解説します。
SNS連携型:フィードやストーリーズからの直接購入
InstagramやTikTokなどのSNSとEC機能を連携させ、投稿やストーリーズから直接購入ページに遷移できる形式です。
例えば、Instagramのショッピングタグを使えば、投稿からそのまま購入へと進むことができます。
この型は、広告っぽさがでずに、自然に購入までの導線を作れる点が強みです。
ビジュアル訴求と相性が良いファッションやコスメ、ライフスタイル系の商品におすすめの型です。
CtoC型:個人間取引の促進
メルカリやBASEなど、個人同士が自由に商品を販売・購入できるプラットフォームを利用した型です。
CtoC型は消費者が所有している商品を出品するため、公式サイトでは見つけられない貴重な商品に出会えたり、通常よりも安価に購入できたりする点がメリットです。
また、事業者にとっては、低コストかつ個人の裁量によって自由に運営できる点も大きなメリットです。
なお、CtoC型のソーシャルコマースでは、重大なトラブルが起こらない限り、企業が取引に介入することはありません。
グループ購入型:共同購入による割引システム
グループ購入型とは、中国のPinduoduoやアメリカのグルーポンのように、複数人で同時購入することで割引価格が適用される仕組みです。
購入したい人の人数が規定値を満たすとクーポンが発行されて割引が適用されるため、購入を呼びかけるためにSNSを活用し、ユーザーが自発的に商品を拡散する点が大きな特徴です。
例えば、通常1つ5,000円の商品が、10人で同時に購入すると4,000円で購入できるといったモデルです。
グループ購入型は中国で主流のソーシャルコマースで、日本国内ではまだ注目されていませんが、今後注目されていく可能性があります。
レコメンド型:友人やインフルエンサーのおすすめ
レコメンド型は、消費者が信頼する人物、例えば、友人やインフルエンサーが紹介したことをきっかけに商品を購入するスタイルです。
SNSでのレビューや投稿、ライブ配信での商品紹介などが該当します。
売り上げを伸ばすために、インフルエンサーにPRを依頼することはレコメンド型の代表例です。
ユーザーキュレーション型:ユーザーが選んだ商品の紹介
ユーザーキュレーション型は、ユーザー自身が選んだ商品を紹介するスタイルです。
投稿型のまとめ記事や、Pinterestのようなプラットフォームを活用した情報発信が該当します。
UGC(ユーザー生成コンテンツ)を軸に構築されており、特定のジャンルに精通したファンが目利き役として機能します。
その人の紹介であれば信頼できるといった面では、レコメンド型と共通点も多い型です。
ユーザー参加型:商品開発や企画への参加促進
ユーザー参加型とは、ソーシャルメディア上でアンケートや投票を行い、ユーザーの声を商品開発や企画に反映させる方法です。
開発段階から関与してもらうことで「自分たちが作った」という愛着が生まれ、購買意欲を高められます。
例えば、カラーや商品名をSNSで募集することで、自然な形で話題が拡散されエンゲージメントも獲得可能です。
O2O型:オンラインからオフライン店舗への誘導
SNSで得た情報をきっかけに実店舗に来店してもらう流れを作るのがO2O(Online to Offline)型です。
例えば、店舗購入限定のキャンペーン情報をSNSで発信することで実来店を誘導するといった戦略は、O2O型に該当します。
特に飲食店や美容室店舗など、オフラインでの体験が売上に直結する業界との相性は抜群です。
ソーシャルコマースを導入するメリット

ソーシャルコマースの導入メリットは、単に販売チャネルが増えるだけではありません。
以下では、特に重要な5つのメリットを取り上げて解説します。
購入プロセスの簡略化と離脱率の低減
従来の販売方法では「商品を発見→ECサイトに移動→検索・カート追加→購入決定→決済」という複数のステップを経る必要がありました。
しかしソーシャルコマースでは、SNS上で商品を見つけた時点で、アプリ内でそのまま決済まで進むことができます。
SNS上で完結できる購入体験は、ユーザーの離脱や購買意欲低下を大幅に抑えることが可能です。
特に、商品の発見から数回のタップで購入できる利便性は大きな武器となり、ECサイト全体の売上向上も期待できるでしょう。
若年層を中心としたターゲットへのリーチ拡大
Z世代やミレニアル世代の若年層は、情報収集をSNSで完結させる傾向があります。
つまり、SNSを活用することで若年層に効果的にアプローチが可能なのです。
その上でソーシャルコマースを活用すれば、自然な形で商品を宣伝・販売できます。
顧客エンゲージメントの強化とファン育成
ソーシャルコマースでは、SNSを通じてユーザーとの関係性を深めることも可能です。
商品に関する投稿へのコメントやシェア、ライブ配信中のチャットといった行動を通じて、ユーザーは積極的にブランドと関わることができます。
こうしたエンゲージメントからブランドへの愛着が生まれていき、中長期的には「ファン化」や「リピート率向上」へとつながっていきます。
公式アカウントで継続的に接点を持ちながら、フォロワーとの関係性を築いていきましょう。
ユーザー生成コンテンツ(UGC)による信頼性向上
企業の一方的な広告よりも、実際に商品を使ったユーザーの口コミの方が、他の消費者にとっては信頼性の高い情報です。
ソーシャルコマースでは、ユーザーが投稿する写真・動画といったUGC(ユーザー生成コンテンツ)が自然と蓄積されていき、企業の資産として機能します。
また、UGCを企業側がリポストや二次利用することで、広告素材としても活用可能です。
良い口コミやレビューといったUGCが増えていくことで、自然と信頼性が向上していくことが期待できます。
低コストでの運用開始が可能
従来のEC販売には、サイト設計や決済機能の連携、集客施策など初期投資がかなりかかっていました。
一方、ソーシャルコマースはSNSアカウントを開設し、基本的な投稿・導線設計を行えば、比較的低コストでスタート可能です。
InstagramやTikTokは無料でビジネスアカウントを作成でき、ショップ機能を利用すれば、最初から本格的な販売導線を構築できます。
初期コストを抑えながら、販売チャネルを増やしたい方や企業にとって、低コストな点は大きな魅力でしょう。
ソーシャルコマース導入における注意点と対策

ソーシャルコマースは多くのメリットがありますが、リスクや注意点もあります。
特にSNSという特性上、トラブルがすぐに拡散されたり、継続的な運用が求められたりするため、事前に対策を講じておくことが重要です。
以下では、4つの注意点とその対策を紹介します。
SNSアカウント運用の負担が継続的に発生する
ソーシャルコマースでは、SNSアカウントの運用がすべての起点になります。
そのため、定期的な投稿やキャンペーンの企画、コメント対応など、継続的な業務負担が避けられません。
また、アルゴリズムの変化も激しく、広範な露出を獲得するためには、戦略的なコンテンツ設計が必要です。
対策として、投稿スケジュールや運用ルールを明文化し、社内または外注で運用体制を整備しましょう。
炎上リスクを考慮した運用が必須になる
SNS上での運用には「炎上リスク」が常につきまといます。
誤解を招く表現や個人情報の扱い方、ユーザー対応の不備など、小さなことでも拡散されると信頼が失われてしまう可能性があります。
対策としては、ガイドラインも作り、投稿前のチェック体制を強化することが重要です。
また、万が一の事態に備え、炎上対策のマニュアルを事前に整えておくこともおすすめです。
プラットフォーム依存のリスクと独自ドメインECとの連携が課題になる
ソーシャルコマースは、SNSに依存した販売モデルです。
そのため、アルゴリズム変更や機能の制限、アカウント停止などにより、売上や集客に大きな影響が出るリスクがあります。
また、ソーシャルコマースが主流になりすぎると、自社のECサイトへの流入が減少し、データの蓄積が難しくなるケースもあるでしょう。
対策としては、SNSと自社ECサイトを連携させた運用を意識しましょう。
例えば、SNSからの流入をトラッキングできるようにするなど、データ活用の仕組みを併せて構築することが重要です。
短期的な成果が出にくい可能性がある
ソーシャルコマースは、リスティング広告やSNS広告のように即効性のある施策ではありません。
SNSの特性上、アカウントがさまざまなユーザーにリーチするには時間がかかり、リーチ後もフォロワーとの関係性ができるまで購買につながらないケースが多く見られます。
そのため、「すぐに売上につながらない」「手間ばかり増えた」といった考えに陥りやすく、運用が続かないケースも多いです。
対策としては、売上だけでなく「フォロワー増加数」「エンゲージメント率」「再訪率」など中長期的な指標もKPIに設定し、効果を可視化しながら運用を続けることがおすすめです。
まとめ
従来の検索中心型のEC販売から、SNS上で共感や体験を起点とする「ソーシャルコマース」へとシフトしつつあります。
ソーシャルコマースには、SNS連携型・グループ購入型・レコメンド型などさまざまな販売形式があり、自社の商材やターゲット層に合わせて選択することが重要です。
ソーシャルコマースは、広告費を抑えながら集客・販売ができる一方で、継続的な運用体制や炎上リスクへの備えなど、成功するためには戦略的な運用が求められます。
「売り込まずに売る」を意識して、フォロワーとの関係を大切にしながらソーシャルコマースを活用していきましょう。
ソーシャルコマースに関するよくある質問
- ソーシャルコマースはどのSNSで始めるのが効果的ですか?
- 商品ジャンルやターゲットによって異なります。例えば、Instagramはビジュアルでの訴求力が高いため、アパレル・美容系と相性が良いです。また、年齢層から考えて、Z世代を狙うならTikTok、30〜40代以上ならFacebookといった決め方もおすすめです。
- 自社ECサイトを持っていない場合でもソーシャルコマースは始められますか?
- はい、ShopifyやBASEといった外部サービスと連携すれば、自社サイトがなくても始められます。
- フォロワーが少なくてもソーシャルコマースは機能しますか?
- フォロワー数が多いに越したことはありませんが、重要なのはエンゲージメント率です。投稿の質やコミュニケーション次第で、フォロワーが少なくとも売上につながります。