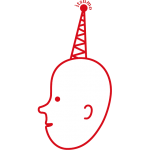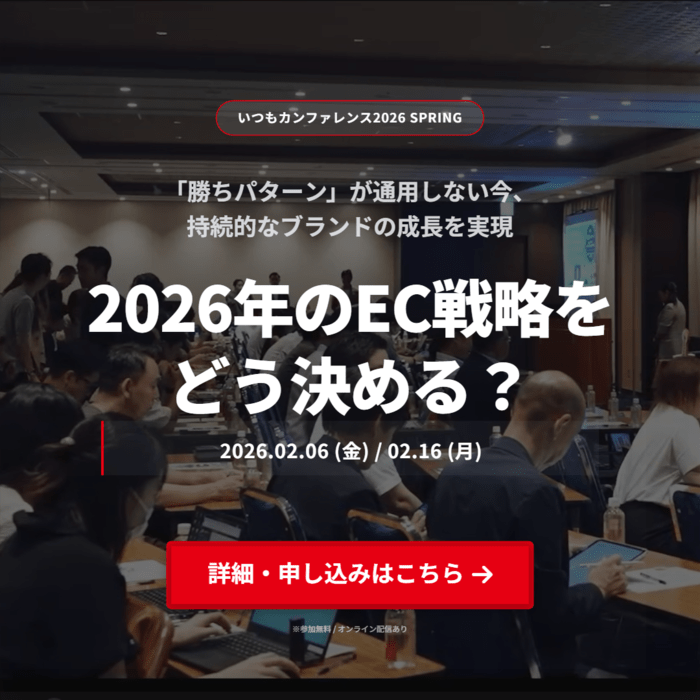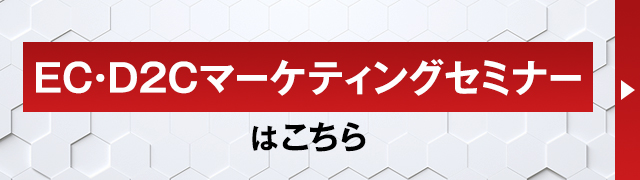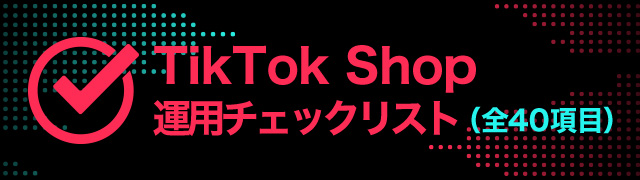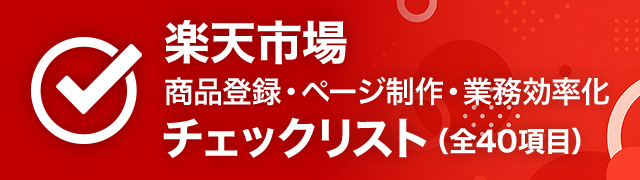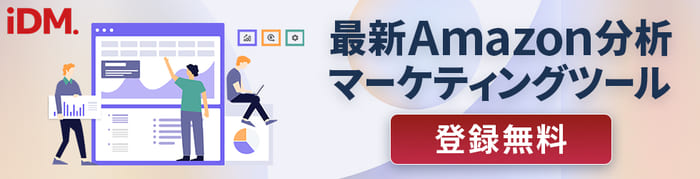EC事業とは?基礎知識からメリット、立ち上げ時の注意点まで解説
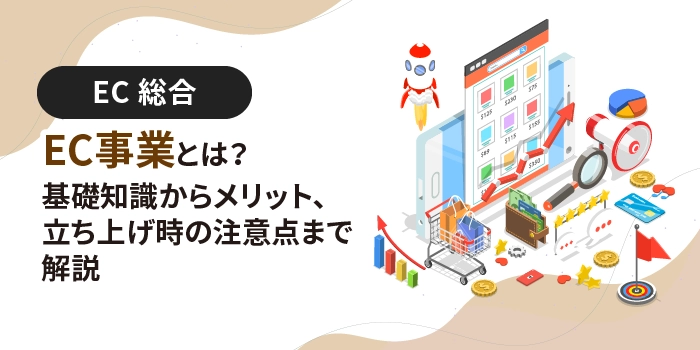
近年、消費者の購買行動は変化しており、オンラインで買い物をする方が急速に増えてきています。
この変化によって近年注目を集めているビジネスが「EC事業」です。
実店舗を持たずに商品やサービスを販売でき、コストを抑えながら幅広い消費者をターゲットにできることから、企業だけでなく個人レベルでも注目されています。
本記事では、EC事業の定義や基礎知識をはじめ、事業を始めるメリットや注意点、立ち上げの方法まで解説します。
これからECサイトを構築・運営したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
※閲覧時期により本記事でご紹介の情報は変更・更新されている場合がございます。
EC事業とは?

EC(Electronic Commerce)事業とは、オンライン上で商品やサービスの売買を行うビジネスのことです。
従来の店舗が必要な販売方法とは異なり、自社で開発したECサイトやAmazonや楽天市場などのプラットフォームを活用することで、実店舗がなくても商品やサービスの売買ができます。
EC事業は、業種・業態を問わず多くの企業が参入しており、それぞれのターゲットのニーズに合わせて、さまざまな形態で展開されています。
新しい事業としてEC事業を始める企業だけでなく、既存の売買チャネルをオンライン化する手法としてEC事業を導入する企業も多いです。
今後はEC事業がビジネスの基盤として、さらに一般化していくと予想できます。
EC事業の主な種類と特徴
EC事業は、取引の主体に応じていくつかの種類に分類されます。
主な4種類の特徴を見ていきましょう。
・BtoC-EC(Business to Consumer)
企業が一般消費者に商品やサービスを販売する最も一般的なモデルです。ECサイトなどを通じて展開され、アパレルや日用品・不動産など、幅広い業種で利用されています。
・BtoB-EC(Business to Business)
企業間で商品・サービスの取引が行われるモデルです。BtoCよりも顧客数は少ないものの取引額が大きくなる傾向があります。
・CtoC-EC(Consumer to Consumer)
個人間で商品・サービスの取引が行われるモデルで、代表例としてはフリマアプリが挙げられます。誰でも出品者・購入者になれる手軽さが特徴で、スマートフォンの普及に伴って市場が急速に拡大しています。
・DtoC-EC(Direct to Consumer)
メーカーが小売業者を介さず、自社サイトなどで、直接消費者に商品・サービスを販売するモデルです。中間マージンを考慮せず商品を提供できる、顧客の声を反映させやすいといった特徴があります。
ひとくちにEC事業といっても、さまざまな種類があるため、どの形態で立ち上げようか迷うでしょう。
それぞれの特徴を理解することで、どの方法が自社に適しているか判断しやすくなります。
拡大を続けるEC市場の現状と今後の展望
日本国内のEC市場は、コロナ禍をきっかけに急成長し、現在も拡大し続けています。
BtoC-EC市場規模は、ほぼスーパーマーケットの市場規模に匹敵しており、消費者の購買行動がオンラインに移行していることは明らかです。
事業者側から見ても、AIやビッグデータの活用によって、よりパーソナライズされたマーケティングや販売戦略が可能となっており、EC事業の可能性はさらに広がっています。
EC事業を始める企業もどんどん増えてきており、今後は、競合との差別化がより求められるフェーズになっていくでしょう。
特に近年は、動画コマースやSNSからの販売導線、AIによるレコメンドなどの機能が続々とリリースされており、「ただのECサイト」では勝ち残れない市場になりつつあります。
そのため、今後EC事業に参入する企業には、マーケティングやブランディングすべてにおいて、競合他社との強い差別化が求められていくでしょう。
参考記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-23365/
EC事業を始める5つの大きなメリット

EC事業には、従来の店舗ビジネスでは得られない多くのメリットがあります。
1.実店舗がなくてもビジネスを始められる
2.販売エリアの拡大
3.24時間販売が可能
4.顧客データの活用
5.ブランド訴求
これからECサイトの構築や運営を検討している方に向けて、上記5つのメリットを紹介します。
実店舗がなくてもビジネスを始められる
EC事業の最大のメリットは、物理的な店舗が不要である点です。
実店舗にかかる初期費用や固定費を無視できる点はとても大きなメリットで、在庫管理や販売もすべてオンラインで完結できます。
たとえば、自社商品を提供するDtoCモデルなら、自社のECサイトを立ち上げて販路を確保できれば、すぐにでもEC事業が始められます。
ECサイトの中には、無料のツールや低コストで始められるサービスも多数あるため、個人や小規模事業者でも始められるほど参入障壁が低いです。
販売エリアの拡大
インターネット上にECサイトを構築すれば、日本国内だけでなく、海外へも商品・サービスを販売できます。
こちらも実店舗が持つ地理的なデメリットを完全に払拭できる、EC事業の大きなメリットです。
店舗ビジネスでは特定の地域に住むターゲット層にしかリーチできませんが、EC事業であれば世界中のターゲット層にアプローチできます。
24時間販売が可能
ECサイトはいつでも注文を受けられるため、24時間365日、自社の商品・サービスが販売可能になります。
消費者側としても好きな時間に購入できるメリットがあり、企業側も運用を自動化することによって業務を効率化できます。
地理的・時間的な要因から生まれる機会損失を失くすことができ、販売機会を最大化することが可能です。
顧客データの活用
EC事業では、顧客の購買履歴やアクセス情報、問い合わせ内容など、あらゆる顧客データを蓄積できます。
この膨大な顧客データを活用することで、顧客ごとにパーソナライズされたマーケティングが行えるようになります。
たとえば、閲覧履歴に基づいたレコメンド機能や、メルマガで再購入を促す施策などが代表的です。
データに基づいて施策を行うことで、販売数・売上の向上が期待できるでしょう。
ブランド訴求
ECサイトでは、自社の世界観やコンセプトを自由に表現できます。
デザインやコピー、商品構成などの統一で、ユーザーに強い印象を与えることができれば、ブランドに共感した上で顧客となってくれる可能性が高いです。
特にDtoCなど、自社ブランドを展開する事業形態においては、ブランド価値を直接伝える手段としてEC事業が非常に有効です。
顧客との信頼関係を築くうえでも、ブランドコンセプトには一貫性を持たせましょう。
EC事業を始める前に知っておくべき注意点

EC事業には多くのメリットがある一方で、成功するために知っておくべき注意点も少なくありません。
市場が拡大を続けている今の環境では、運用体制やマーケティング戦略をしっかりと構築し、競合との差別化を図ることが重要です。
以下では、EC事業を始める前に押さえておきたい3つの注意点を紹介します。
顧客とのコミュニケーション不足を補う工夫が必要
EC事業ではオフラインでの接客がないため、顧客とのコミュニケーションが不足してしまいがちです。
問い合わせ対応が遅れたり、説明が不足したりするとクレームから売上低下につながるケースもあるでしょう。
そのため、FAQの充実やチャットボットの導入、問い合わせフォームの整備など、対面の接客を補える情報をどのように提供するかが重要です。
商品に関する写真や説明文をしっかり作り込むことで、ユーザーの不安を払拭し、購入につなげることができるでしょう。
競合との差別化とSEO対策が必要
EC事業者は無数に存在しているため、競合と比較されることは避けられません。
価格や商品内容だけでなく、サイトデザインや購入までの導線、訴求方法などでも差別化する必要があります。
さらに、検索エンジンからの流入を増やすには、SEO対策も不可欠です。
たとえば、競合の強いカテゴリーであれば、「専門性」「安心感」「限定性」などの価値を明確に打ち出すことで、検索結果でも目立つ存在になれます。
参考記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-20315/
参考記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-20922/
データに基づいた効率的な集客戦略が重要
近年の市場環境では、サイトを作っただけでは商品は売れません。
売上を作り、伸ばしていくためには、データを活用した効率的な集客戦略の立案と改善を継続する必要があります。
SNS広告やリスティング広告、リマーケティングなどのマーケティング手法を活用しながら、アクセス解析やCVR(購入率)をはじめとした数値を定期的にチェックすることが欠かせません。
また、ターゲット層のニーズを明確にし、それに沿って訴求内容や導線設計を考える必要があります。
感覚ではなく、データに基づいて根拠のある仮説を立て、検証・改善を繰り返していきましょう。
参考記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-18062/
参考記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-12450/
EC事業の始め方

EC事業の成功には、事前準備と計画的な実行が欠かせません。
ここでは、EC事業を立ち上げる際に行うべきステップを5段階に分けて解説します。
1.事業計画の策定
2.競合分析と市場調査
3.商品・サービスの選定
4.運用体制の構築
5.予算計画
それぞれの工程には明確な目的と必要な情報があるため、どのステップも飛ばさずに進めましょう。
参考記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-18518/
事業計画の策定
まずは、EC事業の全体像である「事業計画の策定」から始めましょう。
事業計画を考える際には、売上目標やターゲット層、販売形態(BtoC、DtoCなど)、初期費用・ランニングコストなど、さまざまな要素を整理する必要があります。
どのような価値を誰に提供するのか、どの市場に参入するのかといった根本的な部分を明確にすることで、運営していく中で判断軸がブレにくくなります。
参考記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-19249/
競合分析と市場調査
事業を始めるうえで避けて通れないのが「競合分析」と「市場調査」です。
類似商品を扱う企業のECサイトを分析し、価格帯や訴求ポイント、販売導線、SEO施策、広告出稿などの傾向を把握しましょう。
また、ターゲット層の購買行動やニーズに関するデータも重要な資料です。
市場の特性を理解せずに始めてしまうと、後から軌道修正が難しくなるケースが多いため、徹底的に調査しましょう。
商品・サービスの選定
次に、実際に販売する商品やサービスの選定に移ります。
特に以下の観点を重視しましょう。
- 継続的に供給できるか
- 自社の強みを活かせるか
- 独自性・手に取る価値があるか
- 価格と利益率は適正か
「ストーリー性」や「限定性」などのブランド価値を打ち出せる商品を選定すると、独自性が高くなり、価格競争に巻き込まれにくいです。
運営体制の構築
EC事業の運営には、複数の業務を並行して実施できる体制が必要です。
たとえば、以下のような役割分担が考えられます。
- サイト構築・管理(デザイナー、エンジニア)
- 商品登録・在庫管理
- 顧客対応(カスタマーサポート)
- 集客・販促(Webマーケター)
アウトソーシングやツールを上手く利用することで、限られたリソースでも円滑な運用が可能になるでしょう。
参考記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-20199/
参考記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-20639/
参考記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-20750/
予算計画
最後に、立ち上げから軌道に乗るまでの費用をシミュレーションし、現実的な予算計画を立てましょう。
初期費用や広告費、外注費、ツール使用量、送料など、見落としがちな費用まですべて洗い出すことが大切です。
さらに、売上が伸びるまでに想定される期間とその間の赤字額も把握しておけば、精神的にも余裕を持ってスタートが切れるでしょう。
優先度や重要度によって、費用をかける箇所を明確に整理し、費用対効果も意識しましょう。
まとめ
EC事業は、実店舗を構えなくても商品やサービスを販売できるビジネスです。
BtoCやBtoB、DtoCといった複数の種類が存在し、それぞれの特徴やターゲットに応じた戦略が必要となります。
これからEC事業を始めようとしている方は、自社のリソースや目的に合わせて、どの方法が最適かを見極めることが重要です。
ニーズや市場の変化を的確にとらえ、顧客との関係を深めながら、売上を伸ばしていきましょう。
参考記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-11883/
EC事業に関するよくある質問
- 自社ECサイトとECプラットフォームへの出店ではどちらがよいですか?
- ECプラットフォームは集客力がある一方で、手数料や価格競争がネックです。自社ECサイトは利益率やブランド訴求に優れますが、集客には時間とコストがかかります。短期的に売上を立てたい場合はECプラットフォーム、長期的に資産を築きたい場合は自社ECサイトがおすすめです。
- 商品数が少なくてもEC事業は始められますか?
- はい、1〜3商品でも始められます。特に単品での出品や定期購入モデルは、在庫リスクを抑えながら運営可能です。訴求や改善に集中できるため、むしろ最初は商品数を絞ることがおすすめです。
- ITスキルがなくても運営できますか?
- 専門知識がなくても始められるシステム(ShopifyやBASEなど)があります。サポートや外注の活用で業務負担も減らせるため、リソースが少ない場合でも問題ありません。業務に必要な最低限の知識は、運用する中で徐々に身につけることが可能です。